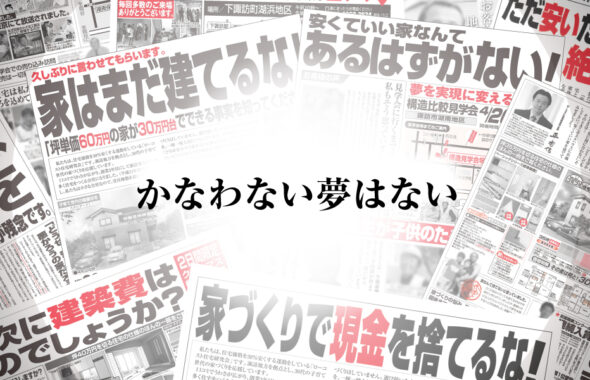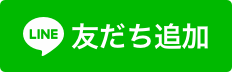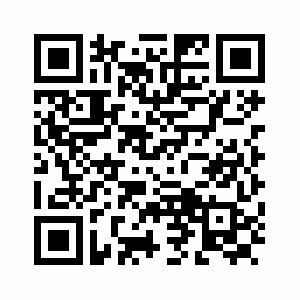【能登半島地震】建物の被害状況から見る「倒壊していない家に共通していたこと」
🏘諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です 😀
色々なことが 見えました。確証できました。大丈夫です。安心してください。
家を建ててください。
建物の被害状況から見る「倒壊していない家に共通していたこと」
視察で注目したのは、倒壊や半壊している街の中で、倒壊していない家があることです。室内の状況は確認できませんが、外観から見て修理が必要ない家もありました。共通しているのは、いずれも新しく、築年数が浅い家という点です。おそらく、建築年数が20年以内で、中には10年も経過していない家もあると思われます。
隣接の建物に対してどうでしょうか。家の4隅に耐力壁を求めた方がいいと、今までは考えていましたが、この通り無傷ですね。ですがこれは、真四角に近い作りからだと思いますし、右側の大きい窓はリビングですね。その上は吹き抜けです。

こちらは朝市の近くにある、焼け野原となった通りを挟んで建っている2軒の家です。どちらもかなり新しい住宅です。揺れが非常に激しかったため、窓ガラスは損傷していますが、外壁面は無傷です。電柱の傾き具合からも、揺れの大きさがわかると思います。



建築された場所にもよるのでしょうけど、古い建屋が並ぶ街や通りに比べて、様子が違うことがわかると思います

あと、写真下の家は基礎(コンクリート側面)を見ると、ここ20年以内に主流となったベタ基礎です。外部に打ち継ぎの目地が見えることから、確実に築年数が浅いということが判ります。
家の4隅もしっかり壁があることから、4隅に耐力壁を確保しています。
上下の窓位置も揃っていることを確認しました。柱、柱で力が伝わっています。

交番は無傷の理由
交番は無傷です。病院、学校、消防署、警察などは、構造強度レベルを、耐震性能3等級レベルが義務付けられています。駐在所もそうなのか?って不明ですが、重い瓦屋根と、家のバランスが悪い家ですが外観的に無傷です。

「能登半島地震」建物の被害状況から「平屋は人命を守れる家」だと言える理由
最後にこの家に注目してください。
何を感じますか・・・?外観が素敵とかかっこいいとか 笑

違います。新しいから・・違います。
着目して欲しいのは、平屋ってことです。今まで現場の被災をレポートしてきましたが、倒壊をしてしまっている家の共通は2階、3階の建屋です。古い平屋を探しましたが倒壊はしていませんでした。 (完全に潰れている建屋は、平屋であったのかどうかは不明ですが・・)
そう、平屋は人命を守れる家ではないでしょうか。ということです。
近年建てた家は損傷は少ない
そして、近年に建てた家は損傷は少ない。これは過去から建築基準法が変わり、耐震性が増してきているわけですが、1981年以前の建物はほぼ倒壊
【旧耐震基準】1981年5月31日以前に建築確認申請が行われた建物に適用
【新耐震基準】1981年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物に適用
【2000年基準】2000年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物(木造)に適用
2000年基準の家では、倒壊を免れるという事実があります。耐震等級3が必須だと言われていますが、個人的には必ずしも耐震等級3でなくても良いのではないかと思っています。安全性を高めておくことは否定しませんが、震災が起きるたびに耐震等級3だの何だのと騒がれますが、現行の最低基準でも十分に倒壊を防げると思います。ただ、室内の影響や家具の倒壊については、強固にしておいた方が良いと思います。
そうした時には、制振ダンパーがきっと役立つはずって思いました。
エルハウスが採用している制振ダンパーはこちら⇩
制振ダンパーミライエ
とにかく「人命を守る」この一点です。今回倒壊した家屋、焼け後の家に花がお供えをされていた様相を多く見ました。まずは命です。
命を守る家。現在の基準法を満たしていれば、、あとは造り手が、丁寧に手を抜かない、確実な施工を施せば大丈夫。あくまでもこれは私の主観ですから・・・。
家づくり、始めたいけど色々と不安。。。
そんな時は、お気軽にご相談くださいね。
建築士&長年の現場監督経験をもつ池原が丁寧にご相談に寄り添います。