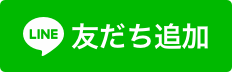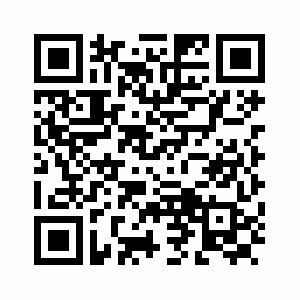設計で必ずぶち当たる壁「リビングの大空間の要望」柱をデザインの一部にした施工例
🏘諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です 😀
どうせなら、大きい空間に住みたいけどね。
設計で必ずぶち当たる壁「リビングの大空間の要望」
設計をしていると、毎回ぶち当たるのが「リビングの大空間の要望」です。笑
建築を依頼される方が『広いリビングにしてほしい』と思う気持ちは痛いほどわかります。
しかし、建築側の立場としては、構造の強度を確保する重要性も理解しているため、もどかしい気持ちになることがあります。

いっそ、構造のことは考えずに、えー、設計側に何とかしてー!とぶん投げたくなる気持ちがないかと言えば、少しだけあります。
木造構造では、柱が建物を支える役割を担っています
木造構造では、柱が建物を支える役割を担っています。そして、その柱と柱の間の距離によって、横架材である梁のサイズが変わります。この梁が床や屋根を支えています。
梁のサイズが大きくなればなるほど、柱と柱の間隔を広げることができます。
しかし、梁のサイズが大きくなると重量が増すだけでなく、本来天井裏に隠れているはずの梁が、天井から室内側に飛び出してしまうこともあります。
ただ、これも木の雰囲気を味わえるデザインとして楽しむことができるので、一概にデメリットとは言えないのですが。

四角い箱を思い浮かべてください
しかし、構造というのは、それだけの問題ではありません。
四角い箱を思い浮かべてください。例えば、12cm角の四角い箱です。
この箱を真上から踏みつけたら、クシャッと潰れてしまいますよね。
では、これを潰れにくくするにはどうすれば良いか?
6cm角の箱を2つくっつけて12cm角の箱を作ると、潰れにくくなります(イメージできますか?)。
さらに、3cm角の箱を3つ並べた場合、もっと潰れにくくなります。
もしかすると、3つ並べれば、上から踏まれても潰れないかもしれませんね。
この考えを木造住宅の構造に当てはめると、柱が多い方が四角い空間が小さくなり、それによって潰れにくい構造になるということです。
柱をデザインの一部にした施工例
でも、リビングの真ん中に柱が立っていたら邪魔ですよね。
そこで、一工夫!その柱をデザインの一部にしちゃおう、という発想です。