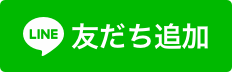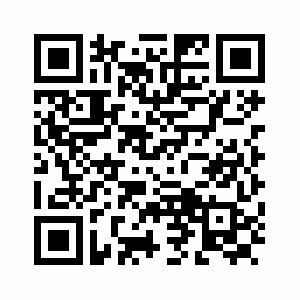【八ヶ岳・硫黄岳】登山ルートやコツと絶景風景写真を一挙公開!
諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です。
前回の続きです
夏沢峠から見上げた硫黄岳は、距離的には近くても、顔を大きく上に向けないと見えない迫力があります。まるで50階建てのビルの真下に立っているような感覚です。
「あっ、ここを登るんだ」という覚悟が必要になりますね。
考え込んでいる暇はない。「行くなら行く!」と決意し、登り始めました。
最初は5分程度で通過する樹林帯を登っていきます。この時の気持ちは、(もう引き返せない。行くしかない。どうか右足は無事でいてくれ…)というもの。
樹林帯を抜けると、一気に急傾斜の登りへと入ります。ジグザグに蛇行しながら、一歩一歩慎重に踏み出し、岩を掴み、登山道沿いに設置されたロープを頼りに上へ、さらに上へと進んでいきます。
ふと振り返ると、瞬く間に景色が開け、素晴らしい眺望が広がります。
さっきの夏沢峠の小屋の屋根が小さく見え、遠くには東天狗岳と西天狗岳の頂上が顔をのぞかせていました。

足元はゴツゴツとした岩が並ぶ中、その間を縫うように登っていきます。
さらに標高が増すごとに、さっきまで見えていた景色がどんどん変わっていきます。
登り続けると、足元はザレ場に変わり、さらに歩きにくくなってきます。
ザレ場では、なんとなく先人たちの歩いた跡を頼りに、一歩一歩慎重に登っていきます。


ここから頂上まではさらに30分ほど!
ザレ場を通過し、大きな岩が並ぶ中を抜けると、ようやく頂上付近が間近に見えてきます。
ところが、ここからがなかなか頂上にたどり着きません。この辺りから頂上までは、さらに30分ほどかかります。


この稜線を登っていく道は、ロープ沿いに歩くだけなので迷うことはありません。
ただし、右側に滑り落ちる危険性があるため、注意が必要です。
振り返ると、景色がさらに広がり、東天狗岳と西天狗岳の頂上が、はっきりと大きく見えてきます。


脚がつって座り込んでいる老夫婦が!
さらに上へ上へと進む途中、老夫婦の方が座り込んでいるのを見かけました。
脚にテーピングらしきものを巻いている最中のようで、気になり声をかけてみると、脚がつってしまったとのこと。
おそらく水分や糖分の補給不足が原因でしょうか。怪我ではないとのことで、時間が経てば大丈夫だと伝え、気にはなりつつも上へ進むことにしました。
時折振り返りながら二人の様子を気にかけ、さらに登ります。後続の方が声をかけている様子を確認し、少し安心しました。
やはり、山では互いに助け合い、声をかけ合うことがとても大切だと改めて感じます。
ちなみに2日前には、中央アルプスや北アルプスで疲労に加え、急な寒さに倒れてしまい遭難するケースが発生していたそうです。

いよいよ硫黄岳頂上だ!
いよいよ頂上だ!1年ぶりか、いや2年ぶりか、硫黄岳の山頂に立つのは。
「とうとうやったな、やり遂げた」という感動が込み上げてきます。
左手には横岳、正面には赤岳、その右には阿弥陀岳。どれもかっこいい頂きです。
「あそこに登ったな、あそこを通ったな」と、昨年や一昨年の登山の記憶がよみがえり、しばし山頂での休憩を楽しみます。
若干風はありますが、硫黄岳山頂特有の爆風ではなく、この日は比較的穏やかです。
それでも、汗をかいた身体は冷えてくるので、上着を羽織って寒さをしのぎます。



背後に爆裂火口。大迫力はどうしても写真では伝わらない。残念

遠くに諏訪湖が見ることができる、やはり今日の天気は最高だ。

硫黄岳は下りのコースも素晴らしい!
下りは登りとは異なるコースを選び、「赤岩ノ頭」と呼ばれる場所へ降りていきます。
降りていく道が遠くまで伸びている景色は、これまた素晴らしいものです。
岩の間を慎重に、時折手を使いながら進みます。かなり慎重に降りたのですが、その理由は言わずともお分かりいただけるでしょう。

赤岩ノ頭に降りて、少し先に進み振り返ると、今日一番の眺望だ。



赤岩ノ頭は分岐点、左に降りると赤岳鉱泉山荘へ。右へ降りるとオーレン小屋。

一番しんどかったのはオーレン小屋までの下り
オーレン小屋までの下りが、一番苦労したというか、しんどく感じました。
右足をかばいながら、階段のように整備されたコースを慎重に一歩ずつ進んでいきます。
途中、登山道を整備している方に出会い、「ありがとうございます。本当に感謝しています」と会釈をしながら、さらに下っていきました。


オーレン小屋に到着し、しばしの休憩をとった後、無事に予定通り帰路につくことができました。今回も八ヶ岳の魅力をたっぷりと感じることができました。
緑色の苔は触るとふわふわで、思わず寝転びたくなるほど。
こんな素晴らしい自然を目の当たりにして、これを大切にし、後世まで伝えていきたいと強く感じました。






お疲れ様でした、最後まで読んでくださりありがとうございました。